
山梨洋靖
2002年に株式会社創造舎を設立。株式会社創造舎 代表取締役。静岡市出身。
杉山浩太
駿府の工房 匠宿 責任者。静岡市出身。元清水エスパルスの選手でキャプテンも務めた。エスパルスでの営業経験を経て、2021年に株式会社創造舎に入社。
「創造舎の社長ってもっと、ロマンスグレーの髪を束ねたみたいな渋い熟年イケオジをイメージしていました」などと人から誤解?されるという山梨洋靖社長。杉山浩太氏と出会ったのは2018年、清水エスパルスの選手を引退してチームの営業スタッフになったばかりの頃でした。それぞれパワフルに活動してきた2人が、今では一緒に匠宿のある泉ヶ谷地区を盛り上げています。2人にとって、故郷って、静岡って、泉ヶ谷ってどんな存在?話しているうちに、この地域のちょっといい未来予想図が見えてきました。
2人が今の匠宿を生み出すまで
―そもそも山梨社長はなぜ浩太さんに匠宿の運営を任せようと思ったんでしょう。
山梨:杉山浩太はうちの社員の義弟なんだよね。初めて会ったのはエスパルスの選手から営業になりたてほやほやのとき。彼が協賛の話を持ってきて、当時はそんなにエスパルスのことを見てたわけじゃなかったんだけど(笑)、乗ることになった。その頃は丁寧に説明するフレッシュな営業マンという感じだったよね。
浩太:知り合いだから営業に行ったわけじゃないですよ。静岡でまちづくりに取り組んでいる会社だからって、それが人生初営業で。そしたら社長がいきなり「ごめん、時間ないからごはん食べながら話そう」って(笑)。話してみると、それまで会ったことないタイプの人でした。めちゃくちゃ怖そうだけどめちゃくちゃやさしいし、パワーあるし。普通じゃない感じ。
山梨:普通だろ(笑)。で、あるとき営業に来た彼と雑談してたら、選手時代から工芸に興味があって、工芸品を集めてるって聞いて「変わってるな」とか言ってたんだよね。そんなことがあったから、匠宿に関わるようになったら一緒にやりたいね、なんていう話したことがあって。で、こうして一緒にやることになったんだけど、ここに来る決断は早かったよね。普通はジュニア時代からエスパルスにいた筋金入りのヤツは辞めないだろうと思ってたんだけど。
浩太:自分から望んで来たんですよ。選手時代なら話は別だけど。
山梨:そもそも選手から営業になる人なんて浩太が初めてだったんでしょ。なんで?
浩太:ちゃんとチームを作る側になりたいと思って。それにはお金を稼ぐところから一度経験してみようという感覚だった。
山梨:そういうことをやっちゃうヤツだから、それなら匠宿まで転身しちゃってもいいじゃんって。サッカーボールから工芸品。
浩太:もともとは静岡の力になれる仕事がしたいというのが根底にあったので、匠宿は一番近いかなと思いました。
山梨:実際一緒にやってみたら、大事な方向性の判断基準は自分とだいたい同じだよね。ここまでOKここからNGとか、感覚とかタイミングにそんなにズレがない。
浩太:匠宿はとにかく誰も何もわからないところから施設づくりを始めたので、山梨社長や仲間とたくさん話し合いました。会社員になってまだ3年で、わからないことは怖くなかった。試行錯誤していくうちに、自分たちらしさがなんとなくできてきて、でもそれにとどまる気はなくて、いつも新しいことをやりたい、そういうところも山梨社長と共通しているかな。責任者としての任務もある中でいつも新しいチャレンジができるのも、いい仲間がいるからできることだと思います。

故郷に尽くすのに理由はない
―山梨社長も浩太氏も静岡市出身。故郷にどんな思いがありますか。
山梨:創造舎は静岡から車で1時間圏内しか建築の仕事を受けないんです。お客様に迷惑をかけたくないのもあるけど、静岡に軸を置く会社なので。仕事があればどこでも行くというやり方は地元の工務店文化を壊す。工務店の技術を継いでくれる子も減る。農家もそうでしょう。僕は静岡がすごく好きだし、自分が生まれた場所は唯一無二。だから静岡に、もっと言えば日本という国に尽くすことに理由はないです。
東京に住んでる江戸っ子の友だちが「地元のある人が羨ましい」って言うんだよね。お盆やお正月に帰るところがないって。だからそう遠くない未来、地元で活躍するのがカッコいいという文化ができてくると思うし、僕はそういう文化をつくりたい。地元で活かす力を培うために東京があるという時代がたぶん来ると思う。
浩太:僕も静岡で生まれたから、同じ静岡出身で僕と10も歳が違わない人が静岡の魅力的なまちをつくってるっていうことがうれしくて。自分の好きなスポットや新しいエリアをつくる人が静岡にいるってことが、僕のやりがいにもなっている。シンプルに、大事ですよね、好きって。
山梨:アメリカみたいに各県がそれぞれの法律をつくるくらい、地方を強くしなければと思います。大地震に備えるためにも分散型にしておかないと。

未来に何が起こったとしても工芸はそこにある
―今、自分たちのミッションだと思っていることは?
浩太:山梨社長はやりたいことやできることをやらないことはリスクだと思ってるんですよね。それを実行して成功させることが僕のミッションだし。自分自身の思いとしては、泉ヶ谷という地域を活かして、工芸を富士山とか駿河湾とかと並ぶ静岡市の魅力の一つにしたいと思っています。工芸の限られた世界ではなくて、泉ヶ谷にある匠宿や旅館とか、地域全体を工芸と絡めて魅力を発信することで、みんなが工芸に注目してくれる。そうすればここに移住する人も、工芸を次につなげる人も増えていくはずです。
山梨:その思いは僕も同じ。そのためにみんなでやってきたんでね。5年10年かけて地域を一つ一つ面で変えていくというやり方は、全国の地方がどう活性化させるか悩んでいる中で、一つの先進モデルになっていくような気がしています。観光に来た人もここの地域づくりのストーリーが注目されて、最終的には静岡の伝統工芸の後継者づくりにまでつなげていけたらいい。極端な言い方だけど、たとえアニメの世界のように何十年後かに環境が劣悪化して、酸素マスクをしないと生きていけないような世界になったとしても、工芸だけはここに残っている可能性を持っていたい。そのためにも、もっといろいろな職人さんが暮らすような地域になるといい。能力を持った人が集まるだけで観光地にもなるという事例を作ってみたいと思っています。

20年後に見たい景色
―では、匠宿を含めた泉ヶ谷地区の、世界に誇れるポテンシャルって何でしょう。
山梨:ここは富士山の眺望も川も海もない、袋小路のようなエリアです。でも、静岡駅から車で15分走るだけで田舎の自然の風景が広がる。それだけでいろんな可能性がありますよ。昔ながらのくねくねした道や戦前の建物が残っている。匠宿の近くにオープンした「ふきさらし湯」は、500メートルくらい離れた駐車場から歩いて来ていただければ、里の風景を楽しんでもらえます。お風呂に浸かれば、軒先の向こうに山が見える。自然の癒しですよね。
浩太:実は今、泉ヶ谷には、匠宿の工芸に限らず静岡らしいものがかなりいろいろ集まってきていて。海の幸がおいしい店もあれば、お茶を使ったスパもある。タミヤのプラモデル体験なんて世界唯一。施設の魅力だけじゃなく、この地区に関わっている人と話すとみんな楽しそうにここを案内するんですよ。誰もがここの仕事が好きだと思っている。そういう、人のポテンシャルもあるかなと思います。
―20年後の泉ヶ谷はどんな景色になっているのでしょうか。
山梨:観光客が泊まる宿や職人の工房兼自宅は増えるだろうし、それに関係するお店やオフィスもできて人口も増えていくだろうし。静岡観光ならとりあえず泉ヶ谷に行けば面白いものがあるよという代名詞になっていたいよね。
浩太:創造舎のやっていることに関係なく、ここに住む人とかここを職場にするという人も増えてほしいですね。
山梨:富士山か泉ヶ谷か、くらいになってるといいよね。今僕たちは泉ヶ谷全体を考えようということをやっているけど、次の10年後はまちの人宿町まで含めて未来図を描きたいよね。畑もつくりたい。丸子と言えば自然薯だし、その他にも育ててみたいものがあって。究極は自給自足できるくらいになったらな。

親がカッコよければ子どもは受け継ぐ
-故郷の未来のために、大切にしているものは何でしょうか。
山梨:昔の商店街がなんで廃れていったのかというと、教育なのかなと思う。商売をやってる親が子どもにあんたたちはこの商売はやめなと言って育ててしまったらやる人がいなくなってしまう。でも、別の仕事に就職した子たちは幸せなのかな。めっちゃこだわりの価値あるものを受け継ぐ方が幸せだったかもしれないと思う。もっと親から受け継ぐことに誇りを持てるようにしないとつながっていかない。僕は自分の子どもたちには、建築の仕事でなくてもいいから何か事業をやってみて、遺言だと思っていつか必ず静岡に戻ってきてくれ、と言ってる。いつか静岡のために活躍してほしい、こんな素敵なところはないし、チャンスしかない。東京では一番になれなかったとしても、ここで一生懸命やれば成功を実感することができるって。今静岡にいる子どもたちにちゃんと伝えていけばきっと戻ってくる。その成果が10年後に出てくると思っています。
浩太:うちの娘はまだ小さいけど、創造舎で働いている人たちって、子どもからお父さんやお母さんと同じ仕事をやりたいと言われることが多いみたいで。すごくいいことだと思います。本人が輝いて仕事していれば子どもたちもついてくる。カッコよくいろって山梨社長はよく言うけれど、自信を持ってる人ってカッコいいじゃないですか。そういう人をつなげていくことが静岡の魅力になるんだと思います。
山梨:20年後に僕たちが引退する頃には今一緒に働いている社員の子どもたちが会社にいる。そんな風になったらずっと続いていけるじゃん。自分の仕事を子どもたちにバトンタッチ、そんな会社になっていけたら理想的かもしれないね。バトンタッチできたら退職金多めにするとか(笑)。そんな日が来るように、子どもたちに教育をしていきましょう。
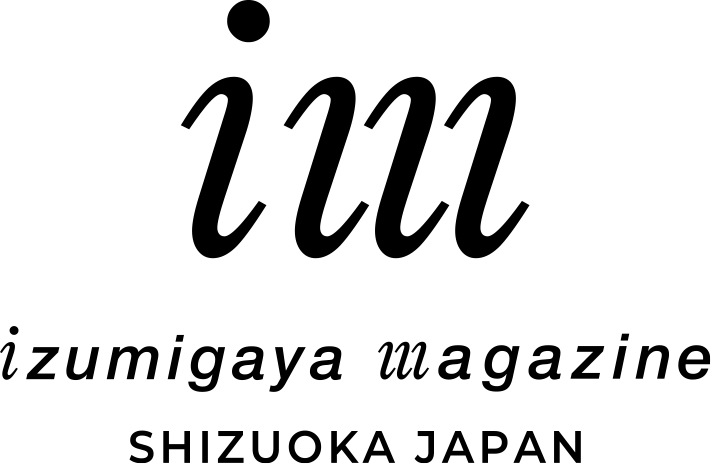


![愛犬と泊まれる静岡市泉ヶ谷のホテル[1HOTEL]](/core/wp-content/themes/im/assets/img/common/booking02.jpg)
![愛犬と泊まれる静岡市泉ヶ谷のホテル[1HOTEL]](/core/wp-content/themes/im/assets/img/common/logo_w_1hotel.svg)